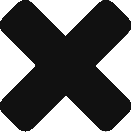わたしたちは日ごろ、明日がやって来るのは当たり前だと思って生きている。しかし、明日がやって来るとは限らないのだということを、コロナ禍は浮き彫りにした。人生には「死」という締め切りがあり、誰も逃れることはできない。そして、その締め切りがいつやってくるのかは誰にもわからない。そのことを意識することで、漫然と過ごしてきた目の前にある「生」が、かけがえのない「生」として尊く感じられた人も多いだろう。自分の人生にとって何が大切で、何が幸せなのか、気づいたという人も多いだろう。
東日本大震災と新型コロナウイルスは、「過疎高齢化にあえぐ地方の生産地」と「超過密都市の消費地」という対極にある現代社会の弱点を突いてきた。両方の弱点の根底に横たわっているのは、すべてを人間の思い通りにしようという「人間中心主義」である。本来は、私と自然は不可分であるが、その不可分のものをわたしたちは無理に切り分けてしまったのだ。こうした人間と自然を分かつ二元論は、気候危機でも問題を拡大させている根本的な要因である。また、人間中心主義は、人間社会の中にも貧困や差別という疎外を生み出す。逆説的だが、人間中心主義は、非人間的になるのである。
わたしたちは、今こそ、この「人間中心主義」を乗り越えていくべきだ。「人間中心主義」から脱却し、私と自然、私と他者が不可分になる社会に変わらなければならない。動植物が活き活きと輝く世界は、人間にもやさしい社会になるのだ。「脱人間中心主義」こそ、人間的なのである。その突破口になるのが、「食」を通じて、人と人、人と自然、都市と地方、生産者と消費者をつないでいくことだ。世なおしは、食なおし。食べる通信やポケットマルシェでは、実際に「脱人間中心主義」に向かった大きな変化が起こっている。来年の3.11で震災から10年目の節目を迎える今、再び岩手県沿岸250キロを自らの足で歩き、47都道府県を行脚する。
輝きを取り戻した「生」
コロナ禍という言葉が示すように、世界の経済社会を停止させ、わたしたちを外出制限に追い込んだ新型コロナウイルスは、確かに「禍」である。しかし、制約の多い外出自粛生活の中で、逆に日常の我慢から解放され、自由や幸福に気付いた人もいたのではないだろうか。例えば、満員電車通勤から解放され、その分、家族とゆっくり過ごす時間が増えた人も多いだろう。コンビニやファストフードに代わり、家で料理をする機会が増えて、普段とは違う食卓を楽しんだ人もいるだろう。日常が崩壊し、「死」がリアリティを持って身近に感じられるようになったことで、人生には締め切りがあることを再認識し、目の前にある「生」が輝きを取り戻したのではないだろうか。
わたしたちは日ごろ、自らの生命を管理し、制御しているつもりでいるけれど、生まれることも、老いることも、病を患うことも、死ぬことも、本来、自分の思い通りにはできない。なぜなら、わたしたちの身体は最も身近な自然であり、人間はそもそも自然をコントロールできないからだ。予定調和な都市で生きるわたしたちはそのことを忘れ、終わりのない日常をこなすように繰り返す毎日を送っていなかっただろうか。戦後の貧困から抜け出し、いつか豊かな生活を手にしようという「未来に置かれた目的」のために「今」を手段として犠牲にしてきたわたしたち日本人。高度経済成長の時代を経て、すでにその目的を達成し、手段の根拠が失われているにも関わらず、それから変わることもなく、かけがえのない「今」という時間を生きそびれてこなかっただろうか。そのことに気づかせてくれたのがコロナ禍ではなかっただろうか。そして、目の前にある「生」を充溢させようと、人々が自宅で向かった先が、台所と食卓であった。
三重県南伊勢町の漁師である橋本純さんは、コロナ禍で出荷先の飲食店が休業し、行き場を失った真鯛の売り先に困っていた。「今どき自宅で魚を丸ごとさばく人はいないだろうけれど」と躊躇いながらも、ポケットマルシェに出品し、ネット個人直販に初挑戦した。すると、2ヶ月間で5670尾も売れた。生まれて初めて魚をさばく人、命をいただいている実感を持ったという人、実家に帰れないから両親に送ったという人、子供の入学祝いに買ってお祝いしたという人、魚嫌いだった家族が競うように食べ尽くしてしまったという人、同じ真鯛を購入した友達とオンラインでご飯会を楽しんだという人など、多くの人から橋本さんに喜びの声とごちそうさまの感謝の気持ちが寄せられた。食を通じて、他者や自然と触れることが、目の前にある「生」を充溢させていったのである。

だが、私にはこの光景に既視感がある。東日本大震災の直後にも、日常にある当たり前の幸せに気づいたという人が多かったのだ。社会の景色を一変させたこのふたつの歴史的出来事をつないだとき、何が見えるだろうか。
弱点を突かれた都市と地方
自然災害はその時代の社会の弱点を突いてくると言われる。東日本大震災で突かれた弱点とは、過疎高齢化にあえぐ地方の生産地であった。新型コロナウイルスで突かれたもうひとつの社会の弱点とは、超過密都市の消費地だった。対極に見えるふたつの弱点は、実は、コインの裏表の関係にある。
コロナ禍にあっても、東京一極集中は続いている。最新の統計によれば、東京都の人口は初めて1400万人を突破。地方から人口を吸い上げ、膨れ上がり続ける大都市と、やせ細り続ける地方の農山漁村。これは戦後の都市と地方の双方が望んだ結果でもある。高度経済成長期には、地方の農山漁村は工業を担う都市への人的資源の供給源であった。これによって、都市は生産、雇用、所得の面で飛躍的な成長を続け、地方の農山漁村は若年層の人口流出で一人当たりの農業生産性は上昇し続けた。都市の姿は地方の姿の裏返しであり、地方の姿は都市の姿の裏返しなのである。元はひとつなのだから、都市と地方は切り分けられない。
都市と地方はお互いに役割分担し、その関係性は極めて効果的に機能してきた。しかし、成長を遂げて成熟社会に移行して以降、その関係性自体が綻び、共に歪みが目立つようになっている。地方の農山漁村は高齢化を伴う人口減で集落の維持存続が危ぶまれ、大都市は通勤地獄、物価高、待機児童、貧困家庭の問題などが山積している。時代の変化に応じて、都市と地方の関係性を変えていかなければならなかったのに、その関係性は硬直化し、今やそれぞれが日本社会のアキレス腱となってしまった。そこを自然災害に容赦なく突かれている。
過剰な都市化による過密社会が新興感染症の温床となり、グローバリゼーションに乗ってパンデミックは引き起こされた。東日本大震災と、その後、地方各地を襲った水害は、復興の担い手である若年層の人的資源の不足を露わにした。巨大地震や気候危機に伴う大規模水害が待ち受ける中、もはや発災する度に対応に追われるもぐら叩きのような対症療法では持たない。超高齢化社会の到来で財政負担が重くのしかかる一方の日本社会は、いつまで耐えられるだろうか。自然災害を正面から受け止めるのではなく、受け流せる社会へと、構造そのものを変えていかなければならない。それは、都市と地方の関係性を抜本的に見直すことを意味する。同時に、人間の自然への向き合い方、すなわち、すべてを人間の思い通りにしようという「人間中心主義」からの脱却を必要とするだろう。
3.11と新型コロナウイルス
歴史に刻まれたふたつのカタストロフィで、人間社会に甚大な影響を与えた「海」と「ウイルス」という自然。人間にとって、自然はふたつの顔を合わせ持つ。人間に恵みを与えてくれるありがたい自然と、人間に災害をもたらすありがたくない自然。これまで、人間は、ありがたくない自然と折り合いをつけながら、ありがたい自然の恩恵に預かって生きてきた。しかし、「人間中心主義」は、本来は不可分な存在を切り分けて、人間にとって有益で効率的なものだけを自分たちに近付け、そうではないものを遠ざけてきた。そうして、海を視界から遮る巨大防潮堤を作り、ウイルス感染から逃れるために経済社会を完全に止める羽目になる。だが、自然と折り合いをつけて共に生きるとは、一定のリスクを受け入れることで、得られる恩恵を感謝して享受するということだったはずだ。
新型コロナウイルスのような新興感染症はこの半世紀あまりで約40種以上出現している。その発生原因は、森林伐採など自然環境の大規模な破壊によって生息地を奪われた野生動物が病原体を拡散するケースがほとんどだ。気候危機の原因である温暖化ガスも人間の経済活動によって排出されてきた。ありがたくない自然がもたらす一定のリスクを受け入れることを一切拒絶し、ありがたい自然の恩恵だけを根こそぎ奪おうとすることで、ありがたくない自然が巨大なリスクを伴って人間の前に立ち現れているように見える。それは、鏡に写った我々自身の姿でもある。人間と自然を完全に切り分ける二元論は、人間の思い通りにしようという意思の露骨な表れであり、人間中心主義の根幹を成す。
瓦解する人間中心主義
経済的利益だけを追求するために自然を手段化し、生物多様性を攪乱する人間中心主義は、人間自身をも経済活動の手段と見なし、人間個々の尊厳を奪い、人間社会の中にも格差と疎外を生み出す。その結果、人間中心主義は、非人間的とならざるを得ない。その象徴的存在が、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏である。「気候危機はでっち上げだ」とパリ協定を一方的に離脱。人間の思い通りにしようと、引き続き物質的繁栄を目指す拡大路線を突き進むと気勢を上げる。宇宙開発にも野心的だ。民間のロケット開発を牽引するスペースX社のCEOイーロン・マスク氏に最大限の賛辞を送る。「死に徹底的に抗う」と言ってはばからないマスク氏は、人間と機械の一体化を目指す不老不死ビジネスにも躍起になっている。
このような際限のない拡張的な成長路線をひた走るトランピズムは、地球と生命の有限性の突破を目論み、“もうひとつの世界”があること喧伝し、これまで通り、すべてを人間の思い通りにしようという意思を貫徹する姿勢を強める。しかし今、わたしたちが突き付けられている圧倒的現実は、世界各地で発生している記録的な猛暑や豪雨、干ばつ、洪水、山火事、海面上昇、新興感染症の拡大など、人間の生活と生存を脅かす差し迫った危機だ。それは、人間の思い通りにならない世界である。今や、地球を生きる誰もがそのリスクから逃れられない。
新型コロナウイルスがもたらしたパンデミックでは、もはや途上国も先進国も、国内も国外も、あなたも私も区別はなく、すべての国、地域、個人が当事者になった。全人類77憶人一人ひとりが、感染させるリスク、感染させられるリスクの鎖で網の目のようにつながったのである。自分だけが守られた安全圏など、どこにもないということに気づかされたわけだが、これは気候危機も同じである。不可分な人間と自然を切り分けることで、自分だけが守られる安全圏の中に身を置いていたつもりが、その中の安全と外のリスクもまた不可分である世界に突入したのである。つまりは、人間中心主義の崩壊である。わたしたちは否応なしに、人間中心主義の外側に押し出され、もはや その内側に戻ることは不可逆的にできなくなってしまったのだ。
つながりの中で生かされるわたしたち
「海」は人間が生きるために必要な恵みを与えてくれる一方で、ときに津波のように牙を剥いて人間に襲い掛かってくる。「海」はわたしたちを生かし、わたしたちは死ねば海に返る。だからこそ、海は私であり、私は海なのである。同様に、「ウイルス」も人間に必要な免疫を与えてくれる一方で、ときに新型コロナウイルスのように姿を見せぬまま人間に不意打ちをかけてくる。「ウイルス」も元々、わたしたち高等生物の遺伝子の一部が外へ飛び出し、長い旅路の果てに戻ってきたものだ。だから、ウイルスは私であり、私はウイルスなのである。異質な世界にあるように見える私と海、私とウイルスだけれども、両者は切り分けられない。
こうして人は自然に生かされることで初めて生きることができる。同じことは、人と人の間にも言えるのではないだろうか。著しく分業化が進んだ現代社会を生きるわたしたちは、ひとりで生きていくことはできない。生活に必要不可欠な衣食住、電気、ガス、水道、交通、娯楽、趣味など、誰かが生産したモノやサービスを購入することで、生きている。つまり、誰かに生かされているのである。逆に、自分も誰かを生かしているのである。しかし、その誰かの顔はもはや見えない。人間の思い通りにしようという「人間中心主義」を体現してきた大量生産、大量消費、大量廃棄の産業システムは、資源を収奪し、環境を破壊するのみならず、生産と消費を分断し、人と人の関わりを見えなくしてきた。
わたしたちは、もう一度、人と自然、人と人のつながりを再構築しなければならない。
世なおしは、食なおし
では、どのようにして、人と自然、人と人とのつながりをつくっていけばいいのか。その入り口となるのが、誰にとっても身近な「食」である。
わたしたちが、毎日口の中にいれている食べ物は、元をたどればすべて動植物の命である。その命を育てた生産者の思いや苦労を知れば、感謝の気持ちが生まれ、丁寧に調理し、残さず食べ、生産者にごちそうさまを伝えたくなる。手塩にかけて育てた生産物をそんなふうに大事に食べてもらったら、生産者も消費者にありがとうの感謝を伝えたくなる。消費者はお金を食べて生きていくことはできない。生産者はお金がなければ生活していくことができない。だから、お互い様の関係なのである。生産者あっての消費者、消費者あっての生産者。ここでも両者は切り分けられない。生産者と消費者を直接つなぐポケットマルシェでは、日々ありがとうの感謝の言葉が飛び交い、そんなお互い様の関係が可視化されている。
また、食べ物として口から摂取した動植物の分子は、食べた人間の老朽化した細胞やタンパク質の分子と置き換わる。この分解と合成の繰り返しが生きるということだ。だから、わたしたちの体は3日前と少し違うし、1年も経てばまったくの別人である。つまり、動植物は私であり、私は動植物なのである。動植物は自然の中で育まれるから、やはり自然は私であり、私は自然なのである。こうして食べ物の裏側へ目を向けることで、命の鎖の網の目の中にいる自分を自覚していく。自然に生かされる私、生産者に生かされる私。両者が不可分な関係になれば、自然や生産者の悲鳴を我が痛みとして感ずることができる。だから、ポケットマルシェでは、災害時にはより一層、生産者とユーザーの助け合いが盛んに行われている。また、生産者と消費者が直接に結びつくことで、人間の思い通りにしようとする市場流通への依存を弱めた分、環境に配慮した生産方法に変わったという生産者もいる。消費と分断された生産は人間中心主義に陥るが、消費と直結した生産は、脱人間中心主義へと向かうのだ。

そもそも、食は単に生命維持のためだけにあるのではない。そうであるなら、スマホの充電と何が変わろう。本来、人間の食事は栄養補給以外に、人間が人間らしく、文化的に生きる上で不可欠な関係性を育む場であり、そこにかけがえのない幸せがあった。その関係性の意味を因数分解すると、食とは、農業という形での人間と自然のあいだの関係性であり、農産物を生産する生産者とそれをいただく消費者のあいだの関係性であり、家族ないし共食関係という枠のなかでの世代を超えたつながりであり、過去の食慣習を現代に活かし未来に伝えるという意味での時間を超えた関係性であり、調理と食事というかたちでの知性と官能の結びつきなのである。この関係性が重層的である食ほど、記憶に残る幸せな時間となる。
誰も予期せぬコロナ禍で、ポケットマルシェでは多くの生産者と消費者がつながった。生産物の行き場を失い途方に暮れる生産者、外出自粛でストレスフルな生活を余儀なくされている消費者。異質な世界を生きる両者が出会い、互いに支え合い、生産者の「想い」と消費者の「おいしい」を共に分かち合い、想定外の世界を活き活きと楽しんでいた。この生産者と消費者が直接つながるプラットフォームでは、意思ある生産者が花開き、そこに意思ある消費者が呼応する。多数の「生産の物語」と多数の「食卓の物語」が地続きとなり、無数の心温まる物語を生み出す。規格に囚われた既存の流通システムが陥ったコモディティ化とは真逆の、代替不可能な唯一無二の物語を生み出した。それは、人間個々の尊厳が回復した世界でもある。
食べるから、第2のふるさとへ
物語を共に紡いだ生産者と消費者は、やりとりを続ける中で、関係性を育んでいく。

都内在住の30代の女性は、ポケットマルシェを通じて、静岡市のイチゴ農家と出会った。実直な人柄とイチゴの美味しさに魅せられ、リピーターとなった。あるとき、その農家から届いた商品を開けると、おまけにイチゴの苗が入っていた。小学生の息子は初めて見るイチゴの赤ちゃんに目を輝かせ、親子で近所のホームセンターからプランターを買ってきて、マンションのベランダで育てることになった。生育状況を写真で農家に伝え、適切なアドバイスを受けた。そうした交流を通じ、今度は息子が静岡の農園に行ってみたいと言い始め、休日を利用してイチゴ狩りを楽しんだ。東京出身であった女性にとっては、疲れたときにリフレッシュに行ける場所、何かあったら逃げ込める先となる「第2のふるさと」となり、農家は東京に孫ができたようだと生きがいになっている。3月下旬、東京都知事が外出自粛要請を呼び掛けた翌日に買い占めが広がり、都内のスーパーから一時的に食料品がなくなったときも、農家は「困ったときはいつでも食べ物を送るから」と女性に連絡し、安心させた。
具体的な個と個が双方向でつながり、継続すると、そこには、より深い関係が生まれる。生産者と消費者が直接つながるD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)と呼ばれる新しいモノづくりは、エンド・トゥ・エンドのつながりを強める。従来のマスの消費社会では、消費者は数値化・類型化され、埋没していた。生産者も同じだ。それが今、個として浮上し、つながり始めている。個と個が見えてこそ、つながりは生まれるのだ。そして、思いを寄せ合い、喜びや悲しみを分かち合う「拡張家族」のような関係に発展していく。「第2のふるさと」に定期的に通い、関わりを深めていく都市住民のことを私は「関係人口」と名付けた。実際に、東日本大震災の被災地支援に通っていた都市住民から着想を得たものだ。
消える過疎と過密
巨大地震、気候危機が鎌首をもたげる日本では、誰もが難民化するリスクから逃れられない時代となった。思い切って言えば、有事に難民化するリスクを避けるには、平時から流民化しておくことではないだろうか。日ごろから都市と地方を行き来しながら同時並行で生きる複線的人生を送るのだ。テレワークや週休三日制が一般的になれば、絵空事ではなくなる。例えば、平日は東京の会社で働き、休日や長期休暇は、地方の拠点に移動し、森林保全活動に参加したり、耕作放棄地を開墾する。多くの都市住民が定期的に全国各地の農山漁村を訪れる遊動生活をしたら、都市と地方は混然一体とし、過密も過疎も融解する。
たとえ人口が量的に減っても、各年代で能動的かつ主体的に地方の複数の現場に関わる人が増えていくことで、人口の「質的変換」がなされれば、社会は今より活力を増すことだってあり得るはずだ。拡大一辺倒の人間中心主義の外側にある循環する自然の世界に身を置き、触れることは、思い通りにできない自然への畏敬の念も育んでいく。
インターネットの中ではアバターのように複数の自分を持つことは今や当たり前である。固定した組織や土地に縛られずに、複数の働き方と暮らし方を実践する遊動生活は、近代の家族モデルが瓦解している現在の液状化社会とも相性がいい。さらに自然災害多発時代にあっては合理的な生存戦略にもなる。都市で被災したときにはもうひとつの地方の拠点が避難先となるし、この遊動社会はあたかも生物多様性が有するような回復機能を発揮するだろう。地球環境というネットワークの結節点に位置している生物は、結び目が多いほど、結ばれ方が多様であるほど、ネットワークは強靭かつ柔軟で可変的な回復力となる。都市と地方の人間が無数の関わりで結ばれていれば、災害時に生物多様性と同じような回復力を発動できるはずだ。
再び、歩く
東日本大震災の被災地で露呈した都市と地方の分断、生産者と消費者の分断、人間と自然の分断は、すべてを人間の思い通りにしようという意思が生み出した結果でもあった。人間中心主義が、地方の過疎や都市の過密、気候危機という形で人間社会に刃を向けているのだから、都市と地方、生産者と消費者、人間と自然がつながりを回復することで、そこから脱却していかなければならない。自然災害は、その時代の社会の弱点を突いてくる。だが、その度に、弱点を克服する新たな仕組みや価値観が生まれてきた。東日本大震災で生まれた新たな意思が、食べる通信とポケットマルシェを生んだ。
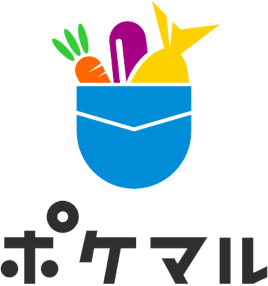

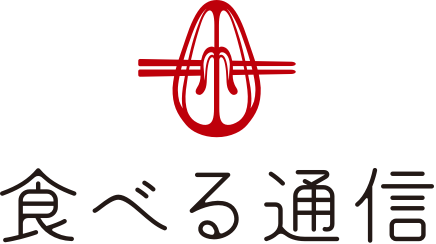

来年の3.11であれから10年を迎える。何もなかったことにはしたくない。その一心で、これまで駆け抜けてきた。この間に、全国キャラバンで日本を5周し、その新たな意思を自らの言葉で生産者に伝えてきた。東京都内では、200回近く車座座談会を開催し、その新たな意思を自らの言葉で消費者に伝えてきた。コロナ禍で、社会の仕組みや人間の価値観が揺らぐ中、今一度、岩手県沿岸250キロを自らの足で歩き、被災地の今に目を凝らし、被災者の今に耳を澄まし、その上で47都道府県を回り、その新たな意思をさらにひとりでも多くの人たちに伝播したい。そう思い、REIWA47CARAVANを決行することにした。来年の3.11までに全国を回り終え、この10年の総括をしたい。
東日本大震災を経験した日本のこれまでの10年間は、コロナ禍を経験した世界の次の10年をどう生きるかの指針となる。気候危機における世界で最も権威ある科学者集団を有する、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が昨年公表した「1.5度特別報告書」は、今のままでは人類が地球で暮らせなくなる大きな危険が生じる分水嶺は2030年にやってくると最後の警鐘を鳴らしている。つまり、人類に残された猶予は、あと10年ということだ。わたしたちの人生と同じで、人類も明日がまたやって来ることは決して自明ではないのだ。だから、この10年を自ら総括し、次の10年の行動を決めたい。
今回の新型コロナウイルス感染爆発の危機に際し、今の行動が2週間後の感染ピークを決めると科学的エビデンスを示されたわたしたち日本人は、今の行動を変容させることで2週間後の未来を変えることができた。ならば、同じように気候危機で人類の生存が脅かされる未来を変えることもできるはずだ。